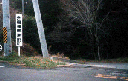 イメージ81K
イメージ81K  イメージ71K
イメージ71K
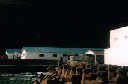 イメージ83K
ニューニッポ(ayu06.gif〜ayu08.gif)
※ニューニッポは、1950年頃の戦後の捕鯨業界再編期に最後に設立された
沿岸捕鯨会社で、日本近海捕鯨→日本近海→ニューニッポ。
イメージ83K
ニューニッポ(ayu06.gif〜ayu08.gif)
※ニューニッポは、1950年頃の戦後の捕鯨業界再編期に最後に設立された
沿岸捕鯨会社で、日本近海捕鯨→日本近海→ニューニッポ。
 イメージ96K
イメージ96K  イメージ70K
イメージ70K
 イメージ102K
次の項目へ
イメージ102K
次の項目へ3-2) 捕鯨の経済的地位 沿岸小型捕鯨に直接従事する者の資料があるのは1985年であるため(107人)、 1985年でみた場合、総労働人口のうちに占める捕鯨産業従事者の割合は 3%弱 ということになる。同一年の資料が得られなかったので参考程度にしかならな いが、1990年時点での総労働人口は3486人、1996年時点での捕鯨産業従事者数 は50人前後であることから、漁業従事者の人数が変わっていないと仮定した場 合 1〜2 %程度ということになる(1990年から1996年の間に、総労働人口は減 少しているものと考えられるので、1996年時点での総労働人口に占める捕鯨従 事者の割合は、若干高めに出ることが予想される)。 また、1985年の資料に基づき捕鯨産業の純生産を遠洋捕鯨と沿岸小型捕鯨で 従事者人数によって案分すると約 3億円となるが、これは1980年の総純生産の うちの約 3%となる。その後、ミンク捕鯨がなくなっていることを考えると、 現在の捕鯨産業の経済的地位は、決して高くはないと言えよう。 鮎川における捕鯨周辺産業については、「捕鯨問題レポート (2) -―鮎川捕 鯨の過去、現在、未来―- 」より引用する。 | 捕鯨の周辺にある加工・販売など、捕鯨に関連する業種の生産をも含めた場 | 合の経済的な地位については、論ずる資料がない。しかし、まだ捕鯨が隆盛を | 誇っていた時期の1971年(昭和47年)に出版された『日本地誌』の中で、小笠 | 原(当時東北大)は、牡鹿町の捕鯨について次のように述べている。 | | 「........肉は、仙台・石巻・塩釜に陸送され、鯨油も同様で、関連工場とい | えるほどの企業の立地はみられない。わずかに鯨の骨・歯の加工業者が1軒あ | るにすぎない。肉・鯨油も地域外の自企業の加工部門に直送されるから、流通 | 部門に地元企業が介入する余地はない。捕鯨業と地元との関係は、漁期(5〜 | 10月)に処理場で60〜80人ほどの臨時雇用(多くは婦人)がみられるにすぎず、 | また捕鯨船の乗組員となっている者も少ない。町財政にとっては、係船・固定 | 資産税で若干の寄与があるにすぎない」 | | 小笠原以前、1955年(昭和30年)の河北新報に竹内(当時東北大)は、鮎川 | 捕鯨の歴史と展望についてかなり詳細な記述を残している。その中で、鮎川捕 | 鯨の地元経済への貢献についても言及している。それによれば、戦前までは粗 | 雑な鯨肉処理が、かなり不安定ではあったが地元民に鯨肥生産などの「シシの | 分け前」的な生業を与えてきた。しかし、戦後派、経営の集約化とともに「シ | シの分け前」がなくなり、それに対処するために小型捕鯨への進出や沿岸定置 | 網が始められたが、資源的にその前途は多難であり、また捕鯨業の発展とは逆 | に地元労力のさばけ口が狭められつつある傾向があると指摘していた。さらに | 竹内は、鮎川の捕鯨を外部企業への寄生体質ときめつけ、「資源のあり方と技 | 術の進歩の相関によって、豊漁はすでに明日の不漁をその内に醸成しつつある | とさえいえる。そして、最大の漁業たる捕鯨には、特にそれが端的に示されて | いる」と、捕鯨基地としての鮎川の衰退を明確に予言していた。 鮎川における捕鯨の経済的地位についてもうひとつ付け加えれば、それは安 定した産業とは言いにくい側面があったということがあげられる。 たとえば、1931年(昭和 6年)には、不漁続きの上に世界恐慌による不況の 影響が出て鯨油などの在庫が山積みとなり、鮎川港からはすべての捕鯨船が消 え、会社は開店休業状態になったという記録がある。失業者も 200人に達して いたという。この窮状を打開するために、失業救済基金による土木工事(簡易 水道の建設や漁港の整備)が行われた。 聞き取り調査では、「鮎川は過去に何度も不漁や捕鯨産業の再編成などで大 きな影響を受けてきている。商業捕鯨の全面禁止も、そのできごとの中の最後 のひとつであるにすぎない」という指摘があった。こういった過去をふまえて、 1972年のストックホルム人間環境会議で捕鯨モラトリアム勧告が出された頃か ら、鮎川の人々は、捕鯨という産業をいずれは失うことになるであろうという ことを認識し、心の準備をしてきていたという。1987年の商業捕鯨完全中止の 際にはさすがにショックは大きかったというが、しかしそれまで無為に座して 見てきたわけではなく、産業構造の転換などは着実に行われてきていたそうだ。 従って、商業捕鯨完全中止もまた、心理的なショックはもたらしたものの、経 済的なショックはたいしたことがなかったと考える人も多い。 その商業捕鯨完全中止からもすでに10年。「鮎川の経済構造の中で、鯨産業 の衰退というこの歴史的出来事の悪影響は、現在もまだありますか」という問 いに対して、複数の町民は「悪影響はもう終わった」と回答している。 ただし、鯨肉の高騰などもあり、1996年現在、捕鯨産業そのものの採算性は 決して悪くない模様である。聞き取り調査によると、複数の町民は、このこと が「現捕鯨産業側からの捕鯨継続への強力なモティヴェーションとなっている」 と指摘した。 もっとも、捕鯨そのものの採算性はとにかく、漁期が限られるということも あるため、捕鯨産業側も多角化経営に乗り出しており、通年産業として成立し 得るよう構造改革の努力も行っているいることにも触れておかねばなるまい。 たとえば外房捕鯨は、ギンザケ養殖を軌道に乗せ、1991年からは、より付加価 値の高いヒラメの養殖へのチャレンジを開始している。 牡鹿町及び鮎川浜における、現実の中の「捕鯨の経済的地位」と、あたかも 捕鯨がなくなれば町が滅亡するというような捕鯨継続・再開に向けての主張の 間には、大きな落差がある。それは、すでに町の中でも少数派にすぎない捕鯨 産業従事者・現在の捕鯨で潤っている者によって捕鯨継続・再開の運動が行わ れているという可能性を、強く示唆するものである。報道などを通じて知るこ とができる捕鯨に関する主張が果たして牡鹿町全体の声であるのかどうかとい う論点については、更なる調査が必要であると言えよう(注:ほかの要因とし ては、捕鯨を存続するという方針が国による大規模遠洋漁業を擁護するための ツールとして使われているという側面があり、この指摘は町民からも聞くこと ができた。しかしこれは、鮎川浜の地域捕鯨や、牡鹿町の漁業といった本来の 論点とは、あまり関係がないもののように思われる)。 【写真】 外房捕鯨(ayu03.gif〜ayu05.gif)イメージ81K
イメージ71K
イメージ83K ニューニッポ(ayu06.gif〜ayu08.gif) ※ニューニッポは、1950年頃の戦後の捕鯨業界再編期に最後に設立された 沿岸捕鯨会社で、日本近海捕鯨→日本近海→ニューニッポ。
イメージ96K
イメージ70K
イメージ102K 次の項目へ
タイトルページに戻る。