3-7) 牡鹿町の人口の推移
牡鹿町の現状に関して、最後に、過疎化について触れておく。本項目では、
しばしば主張される「捕鯨がなくなれば町を維持できない」とする主張の真偽
を、人口の推移という見地から検証することを目的とする。
以下の数表は、牡鹿町全域及び各集落の1960年比の人口割合をまとめたもの
である。北西隣接の石巻市の地域別推移、北東隣接の女川町全域の推移も、比
較のために掲載した。
原則として1960年の人口を 100とし、5年おきの人口を百分率で表示した。
石巻市と合併した一部地域については古い人口資料が入手できなかったため、
資料が入手できた最初の年を 100として算した(そのため、その地域の数字は、
他の地区の数字とは、直接比較はできない)。
<資料・人口の推移>
初年人口 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990
---------------------------------------------------------------------
牡鹿町全域 13405 100 89.3 78.9 71.1 63.0 58.2 50.5
---------------------------------------------------------------------
<牡鹿町・旧鮎川村地区>
旧鮎川村域(*1) 8022 100 87.8 78.0 69.9 59.2 52.4 43.6
鮎川浜 3854 100 88.4 81.1 75.8 63.6 58.2 53.1
十八成浜 1000 100 85.8 79.3 68.8 58.3 48.2 43.3
長渡浜(*2) 2029 100 92.2 77.4 64.5 56.0 48.2 35.4
網地浜(*2) 1139 100 79.6 67.8 60.6 51.1 43.7 26.4
---------------------------------------------------------------------
<牡鹿町・旧大原村地区>
旧大原村域(*3) 6442 100 89.0 77.9 70.8 65.6 63.2 54.9
小網倉浜 463 100 91.3 76.6 66.9 58.3 56.5 50.5
大原浜 683 100 85.6 70.5 63.2 55.9 50.6 46.9
小淵 1041 100 99.4 91.4 84.6 78.5 74.5 70.0
給分浜 468 100 80.9 71.7 61.5 73.7 73.7 69.4
新山浜 272 100 90.4 77.2 65.8 59.5 58.8 53.6
泊浜 464 100 95.9 88.5 77.3 72.6 71.9 57.1
谷川浜 591 100 88.6 73.0 63.9 55.4 49.7 47.3
大谷川浜 266 100 84.2 74.8 69.5 62.0 59.3 56.3
鮫浦浜 209 100 86.1 76.0 74.6 77.9 109.5 96.6
前網浜 207 100 97.1 81.1 74.8 71.4 62.3 55.5
寄磯浜 639 100 91.5 84.9 85.6 82.6 84.8 74.1
---------------------------------------------------------------------
<現石巻市区域>(*4)
旧石巻地区 62360 100 109.9 117.9 121.6 127.1 129.6 128.6
田代 1020 --- 100 84.2 65.0 46.2 28.8 19.2
蛇田 5510 100 105.5 171.6 263.0 299.4 312.7 310.6
荻浜 3868 100 91.1 60.9 51.8 45.7 41.5 37.8
渡波 14385 100 97.8 111.1 114.0 120.1 122.4 125.0
稲井 6998 --- --- 100 91.7 89.3 87.1 84.1
---------------------------------------------------------------------
<女川町>
女川町全域(*5) 18002 100 100.4 98.2 94.1 89.4 84.6 77.8
(国勢調査の数値より算出)
*1 旧鮎川村は、牡鹿町南部(牡鹿半島先端部)および網地島からなる。
*2 長渡浜と網地浜は、牡鹿半島南西の網地島にある。この2地域の人口推移
と、石巻市田代(網地島北西の田代島)の人口推移とを比較せよ。島部の
人口減少は、どこも著しい。
*3 旧大原村は、牡鹿町北部であり、石巻・女川に隣接するエリアである。陸
路をたどった場合、旧鮎川村地域と比べると、遥かに交通の便がよい。う
ち、人口減少率が特に低い小淵・給分浜は牡鹿町西海岸北部の中心地であ
り、鮫浦浜は東海岸の北部にあたり女川に近い場所である。さほどはっき
りしたものではないが、半島の付け根から先端に向かうにつれ、過疎化の
進行が激化するというおぼろげな傾向が見える。
*4 石巻は基本的には人口減少にみまわれていないが、地域的に見ればかなり
の差がある。田代は、長渡浜・網地浜と同様に島であり、極めて過疎化の
進行が激しい。蛇田は、石巻市街北方の内陸部で、石巻のベッドタウンで
あり、過疎化とは無縁の状態である。荻浜は、牡鹿半島北西部にあたり、
牡鹿町と接するエリアで、牡鹿町以上に過疎化が進行している。渡波は、
石巻東方地区で、鉄道も通っている地区。稲井は、石巻北東の内陸部。
*5 鉄道が通っている女川町であるが、牡鹿町ほどではないにせよ、やはり過
疎化は進行している。
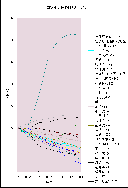 グラフイメージ694K
このデータから読み取れることは、町全体で過疎化は確実に進行しているが、
それでも牡鹿町はよく頑張っているという姿である。また、鮎川浜で特に過疎
の進行が激しいわけではなく、それどころかかなり不利な半島先端部に位置し
ているにもかかわらず牡鹿町の中では中位の過疎進行状況にとどまっているこ
とが読み取れる。満足できる状態ではないにせよ、決して最悪の状況にあると
いうわけではない、と言えようか。
過疎化が牡鹿町にとって極めて深刻な問題であることは確かである。しかし
ながらそれは日本各地の、たとえば交通の便がよくない場所などで一般的に発
生している状況なのであり、牡鹿町及び鮎川浜の過疎化に、個別の特別の事情、
たとえば捕鯨という一産業の衰退というような事情があるようには見受けられ
ない。過疎化は、日本各地で同じように起こっている問題であり、日本におけ
る社会の構造的な問題に由来するものである。牡鹿町の過疎化の進行を食い止
めるには、基本的には日本の社会構造に手をつけなければならないものなので
ある、と言うことができよう。
更に、捕鯨産業と鮎川浜・牡鹿町の人口推移との関係について見てみよう。
<資料・人口推移(*1)>
記録年 鮎川浜 牡鹿町域 記事
--------------------------------------------------------------------
1698年 433人 ( 3916人)
1772年 408人
1774年 408人
1828年 329人
1850年 202人
1887年 332人 ( 3197人)
1888年 376人
1889年 ( 3472人)
1891年 477人
1896年 ( 4473人)
1896年 ( 4406人)
1904年 ( 4981人)
1906年東洋漁業進出
1908年土佐捕鯨・紀伊水産進出
1909年 651人
1910年藤村捕鯨進出
1911年 ( 5608人) 1911年長門捕鯨進出
1915年 1135人
1917年 ( 6996人)
1925年 ( 8016人)
1930年 8559人
1935年 9486人
1940年 9902人
1943年 (10197人)
1946年 2900人
1947年 11798人
1950年 3660人 13226人 1950年日本水産撤退
1955年 3795人 13753人
1960年 3854人 13405人
1965年 3409人 11974人 1965年極洋捕鯨撤退
1970年 3126人 10581人
1971年 (11191人) 1971年外房捕鯨進出
1975年 2925人 10361人
1977年 ( 9522人) 1977年大洋漁業撤退
1980年 2453人 8949人
1985年 2245人 7814人
1988年商業捕鯨終了
1990年 2049人 6773人
*1 牡鹿町域の人口のうち、カッコがついていないものは国勢調査。カッコが
ついているものは複数の別の調査による数値であり、必ずしも連続性が保
障されていない。
(「牡鹿町史」「国勢調査」より作成)
グラフイメージ694K
このデータから読み取れることは、町全体で過疎化は確実に進行しているが、
それでも牡鹿町はよく頑張っているという姿である。また、鮎川浜で特に過疎
の進行が激しいわけではなく、それどころかかなり不利な半島先端部に位置し
ているにもかかわらず牡鹿町の中では中位の過疎進行状況にとどまっているこ
とが読み取れる。満足できる状態ではないにせよ、決して最悪の状況にあると
いうわけではない、と言えようか。
過疎化が牡鹿町にとって極めて深刻な問題であることは確かである。しかし
ながらそれは日本各地の、たとえば交通の便がよくない場所などで一般的に発
生している状況なのであり、牡鹿町及び鮎川浜の過疎化に、個別の特別の事情、
たとえば捕鯨という一産業の衰退というような事情があるようには見受けられ
ない。過疎化は、日本各地で同じように起こっている問題であり、日本におけ
る社会の構造的な問題に由来するものである。牡鹿町の過疎化の進行を食い止
めるには、基本的には日本の社会構造に手をつけなければならないものなので
ある、と言うことができよう。
更に、捕鯨産業と鮎川浜・牡鹿町の人口推移との関係について見てみよう。
<資料・人口推移(*1)>
記録年 鮎川浜 牡鹿町域 記事
--------------------------------------------------------------------
1698年 433人 ( 3916人)
1772年 408人
1774年 408人
1828年 329人
1850年 202人
1887年 332人 ( 3197人)
1888年 376人
1889年 ( 3472人)
1891年 477人
1896年 ( 4473人)
1896年 ( 4406人)
1904年 ( 4981人)
1906年東洋漁業進出
1908年土佐捕鯨・紀伊水産進出
1909年 651人
1910年藤村捕鯨進出
1911年 ( 5608人) 1911年長門捕鯨進出
1915年 1135人
1917年 ( 6996人)
1925年 ( 8016人)
1930年 8559人
1935年 9486人
1940年 9902人
1943年 (10197人)
1946年 2900人
1947年 11798人
1950年 3660人 13226人 1950年日本水産撤退
1955年 3795人 13753人
1960年 3854人 13405人
1965年 3409人 11974人 1965年極洋捕鯨撤退
1970年 3126人 10581人
1971年 (11191人) 1971年外房捕鯨進出
1975年 2925人 10361人
1977年 ( 9522人) 1977年大洋漁業撤退
1980年 2453人 8949人
1985年 2245人 7814人
1988年商業捕鯨終了
1990年 2049人 6773人
*1 牡鹿町域の人口のうち、カッコがついていないものは国勢調査。カッコが
ついているものは複数の別の調査による数値であり、必ずしも連続性が保
障されていない。
(「牡鹿町史」「国勢調査」より作成)
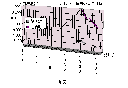 グラフイメージ230K
<資料・鮎川港における鯨の水揚げ/沿岸捕鯨実績と鮎川浜の人口の増減>
年次 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1962 1965 1970 1975 1978 1979 1980
------------------------------------------------------------------------
頭数 278 432 344 714 810 404 785 661 2178 1233 1054 498 628
人口比 98.5 100 88.4 81.1 75.8 63.6
(「捕鯨基地牡鹿町鮎川浜の歴史と現況」「国勢調査」より作成)
グラフイメージ230K
<資料・鮎川港における鯨の水揚げ/沿岸捕鯨実績と鮎川浜の人口の増減>
年次 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1962 1965 1970 1975 1978 1979 1980
------------------------------------------------------------------------
頭数 278 432 344 714 810 404 785 661 2178 1233 1054 498 628
人口比 98.5 100 88.4 81.1 75.8 63.6
(「捕鯨基地牡鹿町鮎川浜の歴史と現況」「国勢調査」より作成)
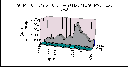 グラフイメージ193K
この2つの資料をつきあわせることでわかることは、鮎川浜が栄えた理由は
明らかに捕鯨産業の進出とシンクロしていると言えるが、過疎状況に陥ったこ
とと捕鯨産業の衰退とは必ずしもシンクロしてはいない、ということである。
人口減少とシンクロしているものは、「捕鯨産業の衰退」ではなく、「大資本
の撤退」であるというべきである。
捕獲実績数が、単年実績・複数年加算実績が混在しているデータであると思
われることから、単純に比較してはならず区間平均を算出して捕鯨の消長を推
測する必要があるが(元のデータから区間平均値などを作成してわかりやすく
することは避けた)、そうするとこの過疎の進行状況は地場産業としての捕鯨
の衰退とは無関係に生じていることがわかる。この過疎の進行は、捕鯨の終了
というような具体的かつ特定の出来事によってもたらされたものではなく、日
本社会の構造の中で牡鹿町という地域が置かれた状況に由来するものだと考え
るのが自然であろう。過疎化をもたらしたものは、直接には大資本の撤退であ
るが、より広く見れば、人口の都市集中という現象の加速であり、第一次産業
の地盤沈下という産業構造の変化が原因であった。
逆に言えば、このことは、捕鯨の継続・再開をしたとしても、若干の好影響
までをも否定することはできないにせよ、牡鹿町・鮎川浜の過疎化を止める力
とはなり得ないのではないかと推測させるに足りることのようにも思われる。
捕鯨の継続・再開は、牡鹿町・鮎川浜を、過疎から救うための切り札とはな
り得ない。捕鯨という産業にはそれほどの力はない。捕鯨に限らず、多少の経
済的寄与をもたらすという程度の産業には、過疎を食い止めるだけの力はない
のであり、総合的な政策による未来の開拓だけが、唯一過疎を食い止め得る道
なのではないだろうか。
もうひとつ、別の興味深い資料がある。
<資料・牡鹿町における人口動態>
年次 自然動態 社会動態 合計
出生 死亡 増減 転入 転出 増減 増減
--------------------------------------------------
1952 424 83 341 1097 1264 -167 174
1953 379 77 302 1237 1475 -238 64
1954 338 95 243 1113 1375 -262 -19
1955 305 70 236 1213 1475 -262 -26
1956 317 69 248 917 1207 -290 -42
1957 236 97 139 803 1058 -255 -116
1958 274 96 178 773 904 -131 47
1959
1960 245 84 161 256 479 -223 -62
1961
1962
1963
1964
1965 207 93 124 402 706 -304 -180
1966
1967
1968
1969
1970 150 74 76 311 601 -290 -214
1971
1972 130 71 50 447 917 -470 -411
1973 149 79 70 361 667 -306 -236
1974 152 91 61 344 565 -221 -160
1975 126 93 33 315 576 -261 -228
1976 112 90 22 319 684 -365 -343
1977 119 84 35 264 540 -276 -241
1978 112 67 55 282 516 -234 -179
1979 109 81 28 269 414 -145 -117
1980 105 93 12 214 473 -259 -247
1981 91 76 15 226 457 -231 -216
1982 102 77 25 319 544 -225 -200
1983 100 66 34 247 357 -110 -76
1984 91 87 4 224 419 -195 -191
1985 75 52 23 188 353 -165 -142
(「牡鹿町史」より作成)
グラフイメージ193K
この2つの資料をつきあわせることでわかることは、鮎川浜が栄えた理由は
明らかに捕鯨産業の進出とシンクロしていると言えるが、過疎状況に陥ったこ
とと捕鯨産業の衰退とは必ずしもシンクロしてはいない、ということである。
人口減少とシンクロしているものは、「捕鯨産業の衰退」ではなく、「大資本
の撤退」であるというべきである。
捕獲実績数が、単年実績・複数年加算実績が混在しているデータであると思
われることから、単純に比較してはならず区間平均を算出して捕鯨の消長を推
測する必要があるが(元のデータから区間平均値などを作成してわかりやすく
することは避けた)、そうするとこの過疎の進行状況は地場産業としての捕鯨
の衰退とは無関係に生じていることがわかる。この過疎の進行は、捕鯨の終了
というような具体的かつ特定の出来事によってもたらされたものではなく、日
本社会の構造の中で牡鹿町という地域が置かれた状況に由来するものだと考え
るのが自然であろう。過疎化をもたらしたものは、直接には大資本の撤退であ
るが、より広く見れば、人口の都市集中という現象の加速であり、第一次産業
の地盤沈下という産業構造の変化が原因であった。
逆に言えば、このことは、捕鯨の継続・再開をしたとしても、若干の好影響
までをも否定することはできないにせよ、牡鹿町・鮎川浜の過疎化を止める力
とはなり得ないのではないかと推測させるに足りることのようにも思われる。
捕鯨の継続・再開は、牡鹿町・鮎川浜を、過疎から救うための切り札とはな
り得ない。捕鯨という産業にはそれほどの力はない。捕鯨に限らず、多少の経
済的寄与をもたらすという程度の産業には、過疎を食い止めるだけの力はない
のであり、総合的な政策による未来の開拓だけが、唯一過疎を食い止め得る道
なのではないだろうか。
もうひとつ、別の興味深い資料がある。
<資料・牡鹿町における人口動態>
年次 自然動態 社会動態 合計
出生 死亡 増減 転入 転出 増減 増減
--------------------------------------------------
1952 424 83 341 1097 1264 -167 174
1953 379 77 302 1237 1475 -238 64
1954 338 95 243 1113 1375 -262 -19
1955 305 70 236 1213 1475 -262 -26
1956 317 69 248 917 1207 -290 -42
1957 236 97 139 803 1058 -255 -116
1958 274 96 178 773 904 -131 47
1959
1960 245 84 161 256 479 -223 -62
1961
1962
1963
1964
1965 207 93 124 402 706 -304 -180
1966
1967
1968
1969
1970 150 74 76 311 601 -290 -214
1971
1972 130 71 50 447 917 -470 -411
1973 149 79 70 361 667 -306 -236
1974 152 91 61 344 565 -221 -160
1975 126 93 33 315 576 -261 -228
1976 112 90 22 319 684 -365 -343
1977 119 84 35 264 540 -276 -241
1978 112 67 55 282 516 -234 -179
1979 109 81 28 269 414 -145 -117
1980 105 93 12 214 473 -259 -247
1981 91 76 15 226 457 -231 -216
1982 102 77 25 319 544 -225 -200
1983 100 66 34 247 357 -110 -76
1984 91 87 4 224 419 -195 -191
1985 75 52 23 188 353 -165 -142
(「牡鹿町史」より作成)
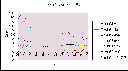 グラフイメージ284K
商業捕鯨が終了したことによって牡鹿町を出ていった人々が存在することは
確かであるが、この資料からは、定住民の流出が過疎化の主な要因であったと
考えることは困難である。牡鹿町の人口減少は、主として「流入が止まった」
ことによって発生したもので、「流出が増えた」ことによってもたらされたも
のではない。それどころか、人口の流出は、捕鯨産業の衰退とともに、著しい
減少を見せているのだ。
牡鹿町の人口減少は、古くからの定住者が域外に立ち去ることによって加速
されたものではない。そういう観点から言えば、「約百年続いた『捕鯨』とい
うバブルがはじけ、牡鹿町は、ようやく本来の姿に戻りつつある」と考えるこ
ともできよう。
この点については、「クジラの文化人類学」の中にも、符合する部分を見出
すことができる。たとえば「日本の捕鯨は過去数世紀の間多くの変遷を経てき
ているが、その中には一貫した特徴が認められる。なかでも顕著な特徴のひと
つは、操業地域と操業形態の柔軟性である。江戸時代の初期から捕鯨操業者た
ちは状況に応じてひとつの地域から他の地域へと絶えず活動の地を移動してき
た」という部分である(18ページ)。鮎川は、捕鯨産業が最後に移動してきた
場所であった。捕鯨産業の多くは、鮎川に用があったのではなく、クジラに用
があったのだ。そして彼らは、鮎川に魅力を感じなくなり、それまでの伝統に
則って、すみやかに鮎川から立ち去っていったのである。
捕鯨終了に由来する人口減について町民に聞き取り調査をしたところ、「し
ょせんは捕鯨と一緒に来た人々だから」という、よそもの扱いの感想もあった。
この感想と人口動態の資料とは符合する。また、「商業捕鯨時代なみの捕鯨が
可能になるならば過疎化は食い止められるかもしれないが、再開ができたとし
てもそれほどの規模にはなり得ない。過疎化を食い止められるほどの捕鯨を再
開すれば、資源の枯渇は免れないであろう」とする意見も、町民から聞くこと
ができた。
<資料・上記「人口の推移」数表の算出元となった人口のデータ(人数)>
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990
---------------------------------------------------------------------
牡鹿町全域 13405 11974 10581 9535 8450 7814 6773
---------------------------------------------------------------------
<牡鹿町・旧鮎川村地区>
旧鮎川村域 8022 7045 6263 5613 4756 4204 3503
鮎川浜 3854 3409 3126 2925 2453 2245 2049
十八成浜 1000 858 793 688 583 482 433
長渡浜 2029 1871 1571 1309 1137 979 720
網地浜 1139 907 773 691 583 498 301
---------------------------------------------------------------------
<牡鹿町・旧大原村地区>
旧大原村域 6442 5734 5020 4561 4229 4073 3542
小網倉浜 463 423 355 310 270 262 234
大原浜 683 585 482 432 382 346 321
小淵 1041 1035 952 881 818 776 729
給分浜 468 379 336 288 345 345 325
新山浜 272 246 210 179 162 160 146
泊浜 464 445 411 359 337 334 265
谷川浜 591 524 432 378 328 294 280
大谷川浜 266 224 199 185 165 158 150
鮫浦浜 209 180 159 156 163 229 202
前網浜 207 201 168 155 148 129 115
寄磯浜 639 585 543 547 528 542 474
---------------------------------------------------------------------
旧石巻地区 62360 68561 73567 75856 79260 80837 80232
田代 --- 1020 859 663 472 294 196
虻田 5510 5814 9458 14495 16497 17233 17116
荻浜 3868 3524 2358 2006 1771 1607 1463
渡波 14385 14071 15995 16405 17280 17613 17986
稲井 --- --- 6998 6418 6255 6099 5887
---------------------------------------------------------------------
女川 18002 18080 17681 16945 16105 15246 14018
(いずれも国勢調査による)
グラフイメージ284K
商業捕鯨が終了したことによって牡鹿町を出ていった人々が存在することは
確かであるが、この資料からは、定住民の流出が過疎化の主な要因であったと
考えることは困難である。牡鹿町の人口減少は、主として「流入が止まった」
ことによって発生したもので、「流出が増えた」ことによってもたらされたも
のではない。それどころか、人口の流出は、捕鯨産業の衰退とともに、著しい
減少を見せているのだ。
牡鹿町の人口減少は、古くからの定住者が域外に立ち去ることによって加速
されたものではない。そういう観点から言えば、「約百年続いた『捕鯨』とい
うバブルがはじけ、牡鹿町は、ようやく本来の姿に戻りつつある」と考えるこ
ともできよう。
この点については、「クジラの文化人類学」の中にも、符合する部分を見出
すことができる。たとえば「日本の捕鯨は過去数世紀の間多くの変遷を経てき
ているが、その中には一貫した特徴が認められる。なかでも顕著な特徴のひと
つは、操業地域と操業形態の柔軟性である。江戸時代の初期から捕鯨操業者た
ちは状況に応じてひとつの地域から他の地域へと絶えず活動の地を移動してき
た」という部分である(18ページ)。鮎川は、捕鯨産業が最後に移動してきた
場所であった。捕鯨産業の多くは、鮎川に用があったのではなく、クジラに用
があったのだ。そして彼らは、鮎川に魅力を感じなくなり、それまでの伝統に
則って、すみやかに鮎川から立ち去っていったのである。
捕鯨終了に由来する人口減について町民に聞き取り調査をしたところ、「し
ょせんは捕鯨と一緒に来た人々だから」という、よそもの扱いの感想もあった。
この感想と人口動態の資料とは符合する。また、「商業捕鯨時代なみの捕鯨が
可能になるならば過疎化は食い止められるかもしれないが、再開ができたとし
てもそれほどの規模にはなり得ない。過疎化を食い止められるほどの捕鯨を再
開すれば、資源の枯渇は免れないであろう」とする意見も、町民から聞くこと
ができた。
<資料・上記「人口の推移」数表の算出元となった人口のデータ(人数)>
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990
---------------------------------------------------------------------
牡鹿町全域 13405 11974 10581 9535 8450 7814 6773
---------------------------------------------------------------------
<牡鹿町・旧鮎川村地区>
旧鮎川村域 8022 7045 6263 5613 4756 4204 3503
鮎川浜 3854 3409 3126 2925 2453 2245 2049
十八成浜 1000 858 793 688 583 482 433
長渡浜 2029 1871 1571 1309 1137 979 720
網地浜 1139 907 773 691 583 498 301
---------------------------------------------------------------------
<牡鹿町・旧大原村地区>
旧大原村域 6442 5734 5020 4561 4229 4073 3542
小網倉浜 463 423 355 310 270 262 234
大原浜 683 585 482 432 382 346 321
小淵 1041 1035 952 881 818 776 729
給分浜 468 379 336 288 345 345 325
新山浜 272 246 210 179 162 160 146
泊浜 464 445 411 359 337 334 265
谷川浜 591 524 432 378 328 294 280
大谷川浜 266 224 199 185 165 158 150
鮫浦浜 209 180 159 156 163 229 202
前網浜 207 201 168 155 148 129 115
寄磯浜 639 585 543 547 528 542 474
---------------------------------------------------------------------
旧石巻地区 62360 68561 73567 75856 79260 80837 80232
田代 --- 1020 859 663 472 294 196
虻田 5510 5814 9458 14495 16497 17233 17116
荻浜 3868 3524 2358 2006 1771 1607 1463
渡波 14385 14071 15995 16405 17280 17613 17986
稲井 --- --- 6998 6418 6255 6099 5887
---------------------------------------------------------------------
女川 18002 18080 17681 16945 16105 15246 14018
(いずれも国勢調査による)
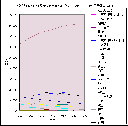 グラフイメージ541K
次の項目へ
グラフイメージ541K
次の項目へ
タイトルページに戻る。
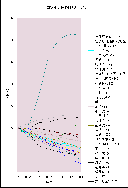 グラフイメージ694K
このデータから読み取れることは、町全体で過疎化は確実に進行しているが、
それでも牡鹿町はよく頑張っているという姿である。また、鮎川浜で特に過疎
の進行が激しいわけではなく、それどころかかなり不利な半島先端部に位置し
ているにもかかわらず牡鹿町の中では中位の過疎進行状況にとどまっているこ
とが読み取れる。満足できる状態ではないにせよ、決して最悪の状況にあると
いうわけではない、と言えようか。
過疎化が牡鹿町にとって極めて深刻な問題であることは確かである。しかし
ながらそれは日本各地の、たとえば交通の便がよくない場所などで一般的に発
生している状況なのであり、牡鹿町及び鮎川浜の過疎化に、個別の特別の事情、
たとえば捕鯨という一産業の衰退というような事情があるようには見受けられ
ない。過疎化は、日本各地で同じように起こっている問題であり、日本におけ
る社会の構造的な問題に由来するものである。牡鹿町の過疎化の進行を食い止
めるには、基本的には日本の社会構造に手をつけなければならないものなので
ある、と言うことができよう。
更に、捕鯨産業と鮎川浜・牡鹿町の人口推移との関係について見てみよう。
<資料・人口推移(*1)>
記録年 鮎川浜 牡鹿町域 記事
--------------------------------------------------------------------
1698年 433人 ( 3916人)
1772年 408人
1774年 408人
1828年 329人
1850年 202人
1887年 332人 ( 3197人)
1888年 376人
1889年 ( 3472人)
1891年 477人
1896年 ( 4473人)
1896年 ( 4406人)
1904年 ( 4981人)
1906年東洋漁業進出
1908年土佐捕鯨・紀伊水産進出
1909年 651人
1910年藤村捕鯨進出
1911年 ( 5608人) 1911年長門捕鯨進出
1915年 1135人
1917年 ( 6996人)
1925年 ( 8016人)
1930年 8559人
1935年 9486人
1940年 9902人
1943年 (10197人)
1946年 2900人
1947年 11798人
1950年 3660人 13226人 1950年日本水産撤退
1955年 3795人 13753人
1960年 3854人 13405人
1965年 3409人 11974人 1965年極洋捕鯨撤退
1970年 3126人 10581人
1971年 (11191人) 1971年外房捕鯨進出
1975年 2925人 10361人
1977年 ( 9522人) 1977年大洋漁業撤退
1980年 2453人 8949人
1985年 2245人 7814人
1988年商業捕鯨終了
1990年 2049人 6773人
*1 牡鹿町域の人口のうち、カッコがついていないものは国勢調査。カッコが
ついているものは複数の別の調査による数値であり、必ずしも連続性が保
障されていない。
(「牡鹿町史」「国勢調査」より作成)
グラフイメージ694K
このデータから読み取れることは、町全体で過疎化は確実に進行しているが、
それでも牡鹿町はよく頑張っているという姿である。また、鮎川浜で特に過疎
の進行が激しいわけではなく、それどころかかなり不利な半島先端部に位置し
ているにもかかわらず牡鹿町の中では中位の過疎進行状況にとどまっているこ
とが読み取れる。満足できる状態ではないにせよ、決して最悪の状況にあると
いうわけではない、と言えようか。
過疎化が牡鹿町にとって極めて深刻な問題であることは確かである。しかし
ながらそれは日本各地の、たとえば交通の便がよくない場所などで一般的に発
生している状況なのであり、牡鹿町及び鮎川浜の過疎化に、個別の特別の事情、
たとえば捕鯨という一産業の衰退というような事情があるようには見受けられ
ない。過疎化は、日本各地で同じように起こっている問題であり、日本におけ
る社会の構造的な問題に由来するものである。牡鹿町の過疎化の進行を食い止
めるには、基本的には日本の社会構造に手をつけなければならないものなので
ある、と言うことができよう。
更に、捕鯨産業と鮎川浜・牡鹿町の人口推移との関係について見てみよう。
<資料・人口推移(*1)>
記録年 鮎川浜 牡鹿町域 記事
--------------------------------------------------------------------
1698年 433人 ( 3916人)
1772年 408人
1774年 408人
1828年 329人
1850年 202人
1887年 332人 ( 3197人)
1888年 376人
1889年 ( 3472人)
1891年 477人
1896年 ( 4473人)
1896年 ( 4406人)
1904年 ( 4981人)
1906年東洋漁業進出
1908年土佐捕鯨・紀伊水産進出
1909年 651人
1910年藤村捕鯨進出
1911年 ( 5608人) 1911年長門捕鯨進出
1915年 1135人
1917年 ( 6996人)
1925年 ( 8016人)
1930年 8559人
1935年 9486人
1940年 9902人
1943年 (10197人)
1946年 2900人
1947年 11798人
1950年 3660人 13226人 1950年日本水産撤退
1955年 3795人 13753人
1960年 3854人 13405人
1965年 3409人 11974人 1965年極洋捕鯨撤退
1970年 3126人 10581人
1971年 (11191人) 1971年外房捕鯨進出
1975年 2925人 10361人
1977年 ( 9522人) 1977年大洋漁業撤退
1980年 2453人 8949人
1985年 2245人 7814人
1988年商業捕鯨終了
1990年 2049人 6773人
*1 牡鹿町域の人口のうち、カッコがついていないものは国勢調査。カッコが
ついているものは複数の別の調査による数値であり、必ずしも連続性が保
障されていない。
(「牡鹿町史」「国勢調査」より作成)
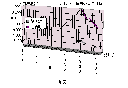 グラフイメージ230K
<資料・鮎川港における鯨の水揚げ/沿岸捕鯨実績と鮎川浜の人口の増減>
年次 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1962 1965 1970 1975 1978 1979 1980
------------------------------------------------------------------------
頭数 278 432 344 714 810 404 785 661 2178 1233 1054 498 628
人口比 98.5 100 88.4 81.1 75.8 63.6
(「捕鯨基地牡鹿町鮎川浜の歴史と現況」「国勢調査」より作成)
グラフイメージ230K
<資料・鮎川港における鯨の水揚げ/沿岸捕鯨実績と鮎川浜の人口の増減>
年次 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1962 1965 1970 1975 1978 1979 1980
------------------------------------------------------------------------
頭数 278 432 344 714 810 404 785 661 2178 1233 1054 498 628
人口比 98.5 100 88.4 81.1 75.8 63.6
(「捕鯨基地牡鹿町鮎川浜の歴史と現況」「国勢調査」より作成)
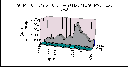 グラフイメージ193K
この2つの資料をつきあわせることでわかることは、鮎川浜が栄えた理由は
明らかに捕鯨産業の進出とシンクロしていると言えるが、過疎状況に陥ったこ
とと捕鯨産業の衰退とは必ずしもシンクロしてはいない、ということである。
人口減少とシンクロしているものは、「捕鯨産業の衰退」ではなく、「大資本
の撤退」であるというべきである。
捕獲実績数が、単年実績・複数年加算実績が混在しているデータであると思
われることから、単純に比較してはならず区間平均を算出して捕鯨の消長を推
測する必要があるが(元のデータから区間平均値などを作成してわかりやすく
することは避けた)、そうするとこの過疎の進行状況は地場産業としての捕鯨
の衰退とは無関係に生じていることがわかる。この過疎の進行は、捕鯨の終了
というような具体的かつ特定の出来事によってもたらされたものではなく、日
本社会の構造の中で牡鹿町という地域が置かれた状況に由来するものだと考え
るのが自然であろう。過疎化をもたらしたものは、直接には大資本の撤退であ
るが、より広く見れば、人口の都市集中という現象の加速であり、第一次産業
の地盤沈下という産業構造の変化が原因であった。
逆に言えば、このことは、捕鯨の継続・再開をしたとしても、若干の好影響
までをも否定することはできないにせよ、牡鹿町・鮎川浜の過疎化を止める力
とはなり得ないのではないかと推測させるに足りることのようにも思われる。
捕鯨の継続・再開は、牡鹿町・鮎川浜を、過疎から救うための切り札とはな
り得ない。捕鯨という産業にはそれほどの力はない。捕鯨に限らず、多少の経
済的寄与をもたらすという程度の産業には、過疎を食い止めるだけの力はない
のであり、総合的な政策による未来の開拓だけが、唯一過疎を食い止め得る道
なのではないだろうか。
もうひとつ、別の興味深い資料がある。
<資料・牡鹿町における人口動態>
年次 自然動態 社会動態 合計
出生 死亡 増減 転入 転出 増減 増減
--------------------------------------------------
1952 424 83 341 1097 1264 -167 174
1953 379 77 302 1237 1475 -238 64
1954 338 95 243 1113 1375 -262 -19
1955 305 70 236 1213 1475 -262 -26
1956 317 69 248 917 1207 -290 -42
1957 236 97 139 803 1058 -255 -116
1958 274 96 178 773 904 -131 47
1959
1960 245 84 161 256 479 -223 -62
1961
1962
1963
1964
1965 207 93 124 402 706 -304 -180
1966
1967
1968
1969
1970 150 74 76 311 601 -290 -214
1971
1972 130 71 50 447 917 -470 -411
1973 149 79 70 361 667 -306 -236
1974 152 91 61 344 565 -221 -160
1975 126 93 33 315 576 -261 -228
1976 112 90 22 319 684 -365 -343
1977 119 84 35 264 540 -276 -241
1978 112 67 55 282 516 -234 -179
1979 109 81 28 269 414 -145 -117
1980 105 93 12 214 473 -259 -247
1981 91 76 15 226 457 -231 -216
1982 102 77 25 319 544 -225 -200
1983 100 66 34 247 357 -110 -76
1984 91 87 4 224 419 -195 -191
1985 75 52 23 188 353 -165 -142
(「牡鹿町史」より作成)
グラフイメージ193K
この2つの資料をつきあわせることでわかることは、鮎川浜が栄えた理由は
明らかに捕鯨産業の進出とシンクロしていると言えるが、過疎状況に陥ったこ
とと捕鯨産業の衰退とは必ずしもシンクロしてはいない、ということである。
人口減少とシンクロしているものは、「捕鯨産業の衰退」ではなく、「大資本
の撤退」であるというべきである。
捕獲実績数が、単年実績・複数年加算実績が混在しているデータであると思
われることから、単純に比較してはならず区間平均を算出して捕鯨の消長を推
測する必要があるが(元のデータから区間平均値などを作成してわかりやすく
することは避けた)、そうするとこの過疎の進行状況は地場産業としての捕鯨
の衰退とは無関係に生じていることがわかる。この過疎の進行は、捕鯨の終了
というような具体的かつ特定の出来事によってもたらされたものではなく、日
本社会の構造の中で牡鹿町という地域が置かれた状況に由来するものだと考え
るのが自然であろう。過疎化をもたらしたものは、直接には大資本の撤退であ
るが、より広く見れば、人口の都市集中という現象の加速であり、第一次産業
の地盤沈下という産業構造の変化が原因であった。
逆に言えば、このことは、捕鯨の継続・再開をしたとしても、若干の好影響
までをも否定することはできないにせよ、牡鹿町・鮎川浜の過疎化を止める力
とはなり得ないのではないかと推測させるに足りることのようにも思われる。
捕鯨の継続・再開は、牡鹿町・鮎川浜を、過疎から救うための切り札とはな
り得ない。捕鯨という産業にはそれほどの力はない。捕鯨に限らず、多少の経
済的寄与をもたらすという程度の産業には、過疎を食い止めるだけの力はない
のであり、総合的な政策による未来の開拓だけが、唯一過疎を食い止め得る道
なのではないだろうか。
もうひとつ、別の興味深い資料がある。
<資料・牡鹿町における人口動態>
年次 自然動態 社会動態 合計
出生 死亡 増減 転入 転出 増減 増減
--------------------------------------------------
1952 424 83 341 1097 1264 -167 174
1953 379 77 302 1237 1475 -238 64
1954 338 95 243 1113 1375 -262 -19
1955 305 70 236 1213 1475 -262 -26
1956 317 69 248 917 1207 -290 -42
1957 236 97 139 803 1058 -255 -116
1958 274 96 178 773 904 -131 47
1959
1960 245 84 161 256 479 -223 -62
1961
1962
1963
1964
1965 207 93 124 402 706 -304 -180
1966
1967
1968
1969
1970 150 74 76 311 601 -290 -214
1971
1972 130 71 50 447 917 -470 -411
1973 149 79 70 361 667 -306 -236
1974 152 91 61 344 565 -221 -160
1975 126 93 33 315 576 -261 -228
1976 112 90 22 319 684 -365 -343
1977 119 84 35 264 540 -276 -241
1978 112 67 55 282 516 -234 -179
1979 109 81 28 269 414 -145 -117
1980 105 93 12 214 473 -259 -247
1981 91 76 15 226 457 -231 -216
1982 102 77 25 319 544 -225 -200
1983 100 66 34 247 357 -110 -76
1984 91 87 4 224 419 -195 -191
1985 75 52 23 188 353 -165 -142
(「牡鹿町史」より作成)
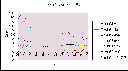 グラフイメージ284K
商業捕鯨が終了したことによって牡鹿町を出ていった人々が存在することは
確かであるが、この資料からは、定住民の流出が過疎化の主な要因であったと
考えることは困難である。牡鹿町の人口減少は、主として「流入が止まった」
ことによって発生したもので、「流出が増えた」ことによってもたらされたも
のではない。それどころか、人口の流出は、捕鯨産業の衰退とともに、著しい
減少を見せているのだ。
牡鹿町の人口減少は、古くからの定住者が域外に立ち去ることによって加速
されたものではない。そういう観点から言えば、「約百年続いた『捕鯨』とい
うバブルがはじけ、牡鹿町は、ようやく本来の姿に戻りつつある」と考えるこ
ともできよう。
この点については、「クジラの文化人類学」の中にも、符合する部分を見出
すことができる。たとえば「日本の捕鯨は過去数世紀の間多くの変遷を経てき
ているが、その中には一貫した特徴が認められる。なかでも顕著な特徴のひと
つは、操業地域と操業形態の柔軟性である。江戸時代の初期から捕鯨操業者た
ちは状況に応じてひとつの地域から他の地域へと絶えず活動の地を移動してき
た」という部分である(18ページ)。鮎川は、捕鯨産業が最後に移動してきた
場所であった。捕鯨産業の多くは、鮎川に用があったのではなく、クジラに用
があったのだ。そして彼らは、鮎川に魅力を感じなくなり、それまでの伝統に
則って、すみやかに鮎川から立ち去っていったのである。
捕鯨終了に由来する人口減について町民に聞き取り調査をしたところ、「し
ょせんは捕鯨と一緒に来た人々だから」という、よそもの扱いの感想もあった。
この感想と人口動態の資料とは符合する。また、「商業捕鯨時代なみの捕鯨が
可能になるならば過疎化は食い止められるかもしれないが、再開ができたとし
てもそれほどの規模にはなり得ない。過疎化を食い止められるほどの捕鯨を再
開すれば、資源の枯渇は免れないであろう」とする意見も、町民から聞くこと
ができた。
<資料・上記「人口の推移」数表の算出元となった人口のデータ(人数)>
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990
---------------------------------------------------------------------
牡鹿町全域 13405 11974 10581 9535 8450 7814 6773
---------------------------------------------------------------------
<牡鹿町・旧鮎川村地区>
旧鮎川村域 8022 7045 6263 5613 4756 4204 3503
鮎川浜 3854 3409 3126 2925 2453 2245 2049
十八成浜 1000 858 793 688 583 482 433
長渡浜 2029 1871 1571 1309 1137 979 720
網地浜 1139 907 773 691 583 498 301
---------------------------------------------------------------------
<牡鹿町・旧大原村地区>
旧大原村域 6442 5734 5020 4561 4229 4073 3542
小網倉浜 463 423 355 310 270 262 234
大原浜 683 585 482 432 382 346 321
小淵 1041 1035 952 881 818 776 729
給分浜 468 379 336 288 345 345 325
新山浜 272 246 210 179 162 160 146
泊浜 464 445 411 359 337 334 265
谷川浜 591 524 432 378 328 294 280
大谷川浜 266 224 199 185 165 158 150
鮫浦浜 209 180 159 156 163 229 202
前網浜 207 201 168 155 148 129 115
寄磯浜 639 585 543 547 528 542 474
---------------------------------------------------------------------
旧石巻地区 62360 68561 73567 75856 79260 80837 80232
田代 --- 1020 859 663 472 294 196
虻田 5510 5814 9458 14495 16497 17233 17116
荻浜 3868 3524 2358 2006 1771 1607 1463
渡波 14385 14071 15995 16405 17280 17613 17986
稲井 --- --- 6998 6418 6255 6099 5887
---------------------------------------------------------------------
女川 18002 18080 17681 16945 16105 15246 14018
(いずれも国勢調査による)
グラフイメージ284K
商業捕鯨が終了したことによって牡鹿町を出ていった人々が存在することは
確かであるが、この資料からは、定住民の流出が過疎化の主な要因であったと
考えることは困難である。牡鹿町の人口減少は、主として「流入が止まった」
ことによって発生したもので、「流出が増えた」ことによってもたらされたも
のではない。それどころか、人口の流出は、捕鯨産業の衰退とともに、著しい
減少を見せているのだ。
牡鹿町の人口減少は、古くからの定住者が域外に立ち去ることによって加速
されたものではない。そういう観点から言えば、「約百年続いた『捕鯨』とい
うバブルがはじけ、牡鹿町は、ようやく本来の姿に戻りつつある」と考えるこ
ともできよう。
この点については、「クジラの文化人類学」の中にも、符合する部分を見出
すことができる。たとえば「日本の捕鯨は過去数世紀の間多くの変遷を経てき
ているが、その中には一貫した特徴が認められる。なかでも顕著な特徴のひと
つは、操業地域と操業形態の柔軟性である。江戸時代の初期から捕鯨操業者た
ちは状況に応じてひとつの地域から他の地域へと絶えず活動の地を移動してき
た」という部分である(18ページ)。鮎川は、捕鯨産業が最後に移動してきた
場所であった。捕鯨産業の多くは、鮎川に用があったのではなく、クジラに用
があったのだ。そして彼らは、鮎川に魅力を感じなくなり、それまでの伝統に
則って、すみやかに鮎川から立ち去っていったのである。
捕鯨終了に由来する人口減について町民に聞き取り調査をしたところ、「し
ょせんは捕鯨と一緒に来た人々だから」という、よそもの扱いの感想もあった。
この感想と人口動態の資料とは符合する。また、「商業捕鯨時代なみの捕鯨が
可能になるならば過疎化は食い止められるかもしれないが、再開ができたとし
てもそれほどの規模にはなり得ない。過疎化を食い止められるほどの捕鯨を再
開すれば、資源の枯渇は免れないであろう」とする意見も、町民から聞くこと
ができた。
<資料・上記「人口の推移」数表の算出元となった人口のデータ(人数)>
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990
---------------------------------------------------------------------
牡鹿町全域 13405 11974 10581 9535 8450 7814 6773
---------------------------------------------------------------------
<牡鹿町・旧鮎川村地区>
旧鮎川村域 8022 7045 6263 5613 4756 4204 3503
鮎川浜 3854 3409 3126 2925 2453 2245 2049
十八成浜 1000 858 793 688 583 482 433
長渡浜 2029 1871 1571 1309 1137 979 720
網地浜 1139 907 773 691 583 498 301
---------------------------------------------------------------------
<牡鹿町・旧大原村地区>
旧大原村域 6442 5734 5020 4561 4229 4073 3542
小網倉浜 463 423 355 310 270 262 234
大原浜 683 585 482 432 382 346 321
小淵 1041 1035 952 881 818 776 729
給分浜 468 379 336 288 345 345 325
新山浜 272 246 210 179 162 160 146
泊浜 464 445 411 359 337 334 265
谷川浜 591 524 432 378 328 294 280
大谷川浜 266 224 199 185 165 158 150
鮫浦浜 209 180 159 156 163 229 202
前網浜 207 201 168 155 148 129 115
寄磯浜 639 585 543 547 528 542 474
---------------------------------------------------------------------
旧石巻地区 62360 68561 73567 75856 79260 80837 80232
田代 --- 1020 859 663 472 294 196
虻田 5510 5814 9458 14495 16497 17233 17116
荻浜 3868 3524 2358 2006 1771 1607 1463
渡波 14385 14071 15995 16405 17280 17613 17986
稲井 --- --- 6998 6418 6255 6099 5887
---------------------------------------------------------------------
女川 18002 18080 17681 16945 16105 15246 14018
(いずれも国勢調査による)
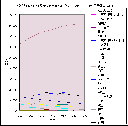 グラフイメージ541K
次の項目へ
グラフイメージ541K
次の項目へ